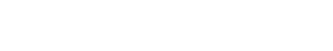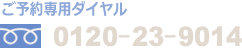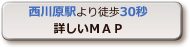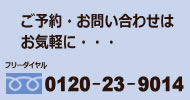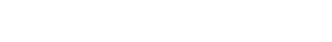くれいしブログ
鶏モモ肉ソテーのキウイソースがけ(2人分)
~材料~
鶏モモ肉(皮なし)・・・180g
キウイフルーツ・・・1個
しょうゆ・・・小さじ2
白ワイン(なければ酒)・・・小さじ1
オリーブオイル・・・小さじ1
作り方
1、キウイフルーツは皮をむき、5㎜の輪切りにします。ポリ袋に材料をすべて入れ、
揉みこみなじませます。空気を抜いて袋の口を閉じ、2時間ほど冷蔵庫で寝かせます。
2、冷蔵庫から出し、20分ほど室温に置いたら、ポリ袋から鶏肉を取り出しフライパンに並べます。調味液をできるだけ切って、ポリ袋に残します。
3、中火にかけたフライパンが温まってきたら、ふたをして中弱火にし、5分加熱します。裏返して、ポリ袋に残った調味液を鶏肉にかけ、ふたをして3分蒸し焼きにします。
4、鶏肉を取り出し、そぎ切りにして皿に盛ります。フライパンに残った調味液を軽く煮詰め、鶏肉にかけます。
- ポイント☆
・甘めの味付けがお好みなら、はちみつ(小さじ1)を調味液に加えて。ただし、焦げやす
くなりますので、加熱時にフライパンをときどきゆすってください。
・キウイのほか、パイナップルに含まれる酵素もお肉を柔らかくしてくれます。
「よく嚙むことが子どものお口の成長によい」といわれていますが、これはホントの話。理由はいくつかあるものの、ここでは顎関節症の面から見てみましょう。
顎関節には、あごの動きの軸となる骨があります。それは下あごの骨(下顎骨)の両端、左右の耳の穴の前あたり存在する「下顎頭」です。役割をたとえるなら、自転車のホイールの軸です。軸と自転車本体との連結がゆるかったら、不安定でガクガクしてこぎづらいですよね。
下顎頭は「発育中心」とも呼ばれている、あごの成長に大切なところ。食べるときの「噛む」作業により下顎頭が適度な刺激を受けると、あごの骨の成長が促されるのです。
もし子供のころケガをして下顎頭が折れてなくなると、あごの成長が悪くなります。下あごが十分に成長せずに、小さいあごになってしまいます。歯の並ぶスペースが狭くなり、歯並びも悪くなりますし、頬まわりの筋肉である咀嚼筋の成長も悪くなって顔がゆがみます(とはいえ、しっかりと治療を受けていれば成長には影響しませんのでご安心を)。
一方、噛む力が弱くても、下顎頭がなくなってしまったときと同様に下あごの成長が悪くなります。これはヒツジの研究でも明らかになっていて、あごの片側の嚙む力が弱いヒツジは、その側の下あごの成長が悪くなります。そして成長すると、顔がゆがんでしまいます。
子供のころからよく嚙んで食べる習慣をつけることは、下あごの成長に大切です。歯ごたえのあるものをよく噛んで食べると、下あごはしっかり働き、正常に成長します。
しかし歯ごたえのないやわらかいものばかりを食べていると、下あごは十分に働かないので成長が悪くなり、その結果歯並びや嚙み合わせに影響を与えることもあります。お子さんの食事を、カレーやハンバーグなどのやわらかいものばかりにするのは考えものですね。
今回は薬の種類について少しだけお話させて頂きます!
薬の種類っていっぱいありますよね?
訳が分からなくなるかとは思いますが、歯科に受診する時に気をつけて欲しい薬の1つをお伝えします!
骨粗鬆症やがんのお薬でビスホスホネートやデノスマブと言ったお薬になります。(製剤なので一般名は異なります)この薬を服用や注射をされている方は原則歯を抜く事ができません。
この薬を服用されている方で歯を抜いてしまうと、ごくまれではありますが顎骨壊死になってしまう恐れがあるからです。
顎骨壊死とは、あごの骨の組織や細胞が局所的に死滅し、骨が腐った状態になることです。 骨が腐ると口の中にもともと生息する細菌による感染が起こり、あごの痛みや腫れ、 膿が出るなどの症状が出てきます!
この薬を処方された方は病院から「歯科にこの薬を服用している事を伝えて下さい」と言う紙をもらうはずです。その紙と一緒にお薬手帳も必ず提出する様にして下さいね。
ビスホスネートやデノスマブ薬を服用する前に、抜かないとダメな歯があれば抜く等する様、歯科に行って検診して下さい。
服用を開始してしまったらしまったで、お口を清潔に保ち、抜かないとダメな歯を作らない為にも定期的に検診やおそうじをしましょうね!
こんにちは!!今回は歯間ブラシについてお話させて頂きます。
歯間ブラシやフロスは
プラークが非常に溜まりやすい
歯と歯が接するコンタクトポイントや、
歯と歯が隣り合ったところの根元まわりをお掃除する道具です。
しかし、歯間ブラシをお使いの方の中には、歯間のサイズに合っていない、
太めの歯間ブラシを使っている方がいらっしゃいます。
歯間のサイズに合っていない、
太めの歯間ブラシだとすき間に入りにくいだけでなく、
歯ぐきが傷ついたり、針金部分が当たって歯の根が削れてしまうことがあります。
歯間ブラシは大は小を兼ねません。
すき間に無理なく入る太さのものを使いましょう。
すき間の大きさは場所によって違いますので、
適切な太さの歯間ブラシを衛生士さんに選んでもらうといいですよ。
毎日頑張ってお口のケアをしているのに、いまいち効果が実感出来ないというあなた。それは歯ブラシのもったいない使い方をしているせいかもしれません。ポイントを押さえたケアの仕方をお教えします!
(もったいないケース)歯みがきは力をいれてゴシゴシ!
→ゴシゴシ磨きを続けていると、歯ぐきが傷つき下がってしまいます。握りこぶしだと力が入りすぎるので歯ブラシはえんぴつを握るようにするか、親指と人差し指で軽く添えるように持ちましょう。そして磨きたいところにやさしく当てて動かします。
歯みがきに一生懸命なあまり、ゴシゴシと力を入れた磨き方になっている方が意外と多いです。
こうした過剰な力での歯みがきは「オーバーブラッシング」と呼ばれ、長期間繰り返されると、歯ぐきが傷つき下がってしまいます。歯ぐきが下がると、虫歯になりやすい歯の根が露出しますし、そこを強い力で磨くと、歯の根の象牙質が削れてしまうこともあります。まじめな人ほど起こりがちで、高校1年生なのに歯ぐきが下がってしまった方もおられます。
歯科では先生または歯科衛生士が歯みがき指導をします。これには歯ブラシの当て方、動かし方だけではなく、力の入り具合の指導も含まれます。初めて指導を受けたときは、「そんなにやさしく磨くんだ!」と驚かれるかもしれませんが、力を入れて磨く必要はないんですよ。
ぜひ力を抜いて磨いてみてください。